« 2011年09月 | メイン | 2011年11月 »
2011年10月26日
2011年11月例会のご案内
山岡鉄舟研究会2011年11月16日開催についてご案内申し上げます。
開催日 2011年11月16(水)
場所 東京文化会館第一中会議室
時間 18:30から20:00
参加費 1500円
発表者 末松正二氏と山本紀久雄が担当いたします。
① 末松正二氏・・・「終戦工作」を12月例会に渡って二カ月ご発表頂きます。本年12月8日は、真珠湾攻撃70周年で、4年後弱の1945年8月に終戦となりました。この終戦を成し遂げた功労者は226事件で奇跡的に一命が助かった二人の海軍軍人であったという、実に不思議な因縁話しから展開されます。昭和史を改めて理解する絶好の機会ですので、ご期待願います。
② 山本紀久雄・・・今年は鉄舟が伊万里県に赴いてちょうど百四十年に当る事から、佐賀県美術館で特別展「山岡鉄舟」(平成23年12月~24年1月15日)が開催されますが、これに合わせ鉄舟が伊万里県(佐賀県)知事として赴任した背景を分析いたします。
佐賀藩は薩長土肥という討幕軍の中で最も科学的に優れていた藩でした。その証明が上野彰義隊をたった一日の戦いで壊滅させた最大要因である「アームストロング砲」を、唯一製造し保有していた事からも分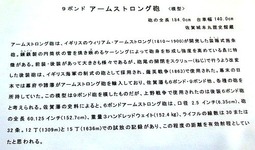
かります。

(佐賀城本丸歴史館展示)
また、幕末時は名君鍋島直正閑叟(かんそう)が藩主で、借金だらけの財政を再建し、豊かな佐賀藩に仕上げ、討幕軍の主力として活躍したわけですから、「県内不穏」という理由で鉄舟が県知事として赴任するのは不思議です。
しかし、明治初年宮武外骨(明治〜昭和期のジャーナリスト)が、難治県として佐賀、鹿児島、高知、山口、石川、愛媛、酒田の7県を挙げているように、明治維新に貢献した薩長土肥の四県が難治県となった理由、特に佐賀県が難治県のトップに挙げられた背景と、鉄舟がどのような治世を行ったのかについて解説いたします。
3.12月例会は以下のように開催いたします。
開催日 2011年12月21(水)
場所 東京文化会館第一中会議室
時間 18:30から20:00
発表者 末松正二氏と山本紀久雄が担当いたします
① 末松氏のご発表は11月に引き続き「終戦工作」です。
② 山本紀久雄の発表は、鉄舟研究を行います。
以上
山岡鉄舟研究会2011年10月開催報告
山岡鉄舟研究会2011年10月開催結果を案内申し上げます。
1.2011年10月開催結果
① 北川宏廸氏・・・ 2006年3月の例会で北川氏が「必勝の剣法はある・・・剣の『理』と『技』をめぐる数理」に続くご発表でした。
「活人剣(かつにんけん)」と「殺人刀(せつにんとう)」
――「必勝の剣法」はある、それが≪武士道≫だ――
この内容、大変参考になり、興味深く、鉄舟剣法を新たなる視点から分析し、加えて、数式と図表を持って解説しておりますので、その全文を北川氏のご了解を受けまして、以下に掲載いたしましたので、是非、ご一読されます事をお薦めいたします。
http://www.tessyuu.jp/archives/2011/10/post_349.html#more
②末松正二氏・・・繆斌(みょうひん)工作について
末松氏には、今年1月に「盧溝橋事件」、4月に「朝日テレビドラマ『遺恨あり~明治13年最後の仇討』についての解説」を頂き、今回は、殆どの人が知らない「繆斌工作」についてご発表を特にお願いいたしました。
繆斌工作とは、1945年3月の戦況悪化著しい時、繆斌が以下の和平条件を持って来日した事実です。
●日本の中国本土からの撤退、
●満州国、台湾は現状維持、
●蒋介石が米国との和平を仲介する
これを当時の小磯首相が最高戦争指導会議に提案しましたが、結局、昭和天皇の反対もあり受け入れなかったのですが、平成3年5月21日に繆斌の慰霊碑を中央区鉄砲稲荷神社に建立したように、顕彰行動をしている人達もいるわけで、その状況を含め当時の生々しい実態を解説頂きました。
11月と12月は末松氏から「終戦工作」についてご発表頂きます。昭和時代を過ごした我々が知るべき「昭和史」を学ぶ機会を大事にしたいと思います。
③山本紀久雄・・・山岡鉄舟という偉大な人物を改めて考察いたしました。
鉄舟はご存じのように、西郷隆盛の「南州翁遺訓」に「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人」と評された人物です。
この評価を現代人の眼から判断すると大きな誤りで、当時の武士階級の常識から判断すべきで、改めて、当時の常識から検討しても鉄舟はけた外れの人物であった背景を解説いたしました。
また、大久保利通が鉄舟を茨城県知事に強く推した背景について、水戸藩と長州藩を財政・産業・人口面から分析し、尊皇攘夷思想を同じく持ちながら、水戸藩は幕末低迷の上人材払底、長州藩は新時代を切り開く人材を多数輩出した、その差と要因について解説いたしました。
「活人剣(かつにんけん)」と「殺人刀(せつにんとう)」
「活人剣(かつにんけん)」と「殺人刀(せつにんとう)」
──「必勝の剣法」はある、それが《武士道》だ──
2011年10月19日
北 川 宏 廸
本日、この山岡鉄舟研究会で是非お話ししたいのは、世の中には何ものにも負けない「必勝の剣法」が存在する、ということについてである。
結論を先に言えば、山岡鉄舟がいう《武士道》とは、実は、この「必勝の剣法」のことをいっているのである。
剣法の実際の「理」と「技(わざ)」を《言葉》で表現するのは、大変むつかしい。
なぜなら、われわれが五感で認識し、判断し、行動(行為)する、剣法の「理」と「技」を表現する言葉の論理は非常に甘いし、また、われわれの認識には、事実から乖離したある種の思い込みやバイアスが含まれているので、実際に起きている事実をそのまま記述すること自体、そもそも不可能であるからだ。
したがって、本稿では、剣法を《言葉》で説明しつつ、そのポイントとなる部分では、自然科学者が自然現象記述の手段として使用する「数式」の力を借りて、この「必勝の剣法」の存在を明らかにしたいと思う。
山岡鉄舟の剣法は
「一刀正伝無刀流」
山岡鉄舟は、自らの剣法を「一刀正伝無刀流」と名付けている。
鉄舟の剣法は、一言でいえば、鉄舟自身が「剣法と禅理」( 明治13年(1880年)、鉄舟45歳のとき )のなかで述べているように、流祖・伊藤一刀斉景久の流れを継ぎ、当時、「一刀流」の達人といわれた師範の浅利又七郎義明から学んだ「一刀流剣法」の奥義を、そのとき、京都天龍寺の管長であった禅僧・滴水から鉗鎚(けんつい)を受けた「無相」の禅理───すなわち、「見性悟入」(太刀を用いないで天道発源の心理の極致に悟入すること)の禅理───に、帰一させたところにある、といってよい。
鉄舟は、「一刀流兵法箇条目録」( 明治15年(1882年)、鉄舟47歳のとき )のなかで、次のように述べている。
「 抑々 当流刀術を一刀流と名付けたる所以のものは、元祖伊藤一刀斉なるを以ての故に一刀流と云ふにはあらず。一刀流と名付けたるは、其気味(注、含むところ)あり。万物大極の一より始まり、一刀万化して、一刀に治まり、又一刀に起るの理あり。又曰く、一刀流は活刀を流すの字義あり。流すは〝すたる〞(以下、括弧〝〞は、筆者)の意味なり。当流〝すたる〞ことを要す。〝すたる〞といふは、一刀に起り、一刀に〝すたる〞ことなり。然れども其〝すたる〞の理通じ難し。於是か、さきより門前の瓦(かわら)と云へるたとへあり。瓦を以て門をたたき、人出で門開く、此時用をなしたる程に、瓦を捨つ可きを、其儘持て席上に通らば、かへって不用品とならん、是を捨てざるゆえなり。業(わざ)も亦然り、打つべきところあらば、一刀を打ちて用をなしたる故、ここに〝すたる〞ことあらば、またおこる、万化すといへども、みなしかり。打って打たざるもとの心となる、これ刀〝すたる〞の至極なり。」
すなわち、鉄舟は、自らの剣法「一刀正伝無刀流」の理を、「一刀に起こり、一刀に〝すたる〞」ところにあるというのだ。
ここで、〝すたる〞という自動詞は、「なきものになる」「あとに残さない」「終わる」「もとに治まる」「はじめに戻る」などの意味で使われている
また、鉄舟は、「剣法邪正弁」( 明治15年(1882年)、鉄舟47歳のとき )のなかで、「一刀正伝無刀流」の極意を、次のように披瀝している。
「夫れ 剣法正伝真の極意者(は)、別に法なし。敵の好む処に随ひて勝を得るにあり。敵の好む所とは何ぞや、両刃相対すれば、必ず敵を打んと思ふ念あらざるなし。故に我体を総て敵に任せ、敵の好む処に来るに随ひ勝つを真正の勝と云ふ。譬へば、箇(はこ)の中にある品を出すに、先ず其蓋を去り、細に其中を見て品を知るがごとし。」
さらに、前述の「一刀流兵法箇条目録」のなかで、「一刀正伝無刀流」のポイントとなる点を、十二箇条あげている。
一、二之目付(にのめつけ)之事
( 敵を見るポイントは、太刀の「切っ先」と、敵の「拳」(こぶし)の2点にある )
二、切落(きりおとし)之事
( 自分の太刀を切り落とすと、何時の間にやら敵の「拳」にあたる、無拍子の拍子 )
三、遠近之事
( 敵の為には打つ間が遠くなり、自分の為には打つ間が近くなること )
四、横竪上下之事
( 横竪上下とは、真ん中のこと。上より来るものは下より応じ、下より来るものは上より応じ、横より 来るものは竪に応じ、竪に来るものは横に応じ、心はいつも中央に在って、気配自由なること )
五、色付之事
( 色付とは、敵の色(気配)に付くな、ということ )
六、目心之事
( 目心とは、目を見るな、心でみよ、ということ )
七、狐疑心之事
( 狐疑心とは、疑心を起こすな、ということ )
八、松風之事
( 松風とは、合気(拍子)を外せ、ということ )
九、地形之事
( 地形とは、順地(つま先下がり)逆地(つま先上がり)のこと。順地は敵を拳下りに打つため有利、 よって敵を逆地におけ、ということ )
十、無他心通之事
( 無他心通とは、敵を打つ一遍の心になれ、ということ )
十一、間之事
( 間とは、敵合いの間のこと。自分の太刀下三尺、敵の太刀下三尺、とみて、六尺の間。一足出さ ねば敵にあたらぬ故、打つもつくも、一足一刀。この間合いが大事 )
十二、残心之事
( 残心とは、心を残さず打て、ということ。心惜しまず〝すたれ〞ということ )
鉄舟が、このように、一ヵ条づつあげて、十二ヵ条目録を掲げたのは、剣法は、一刀よりおこって、万剣に化し、また、万刀一刀に帰す、と考えたからだ。
これはちょうど、一年に十二ヵ月があり、一陽に起こって、万物造化し、陽中陰をめぐみて、万物生じ陰ここに極まりて、年月つくるものと見れば、陰中陽を発して、またいつか青陽の春にかへるようなに、自然の摂理は、必ず陰陽をくりかえす。
したがって、「一刀正伝無刀流」の鍛錬や修業も、「一よりおこりて十二に終る、而してまたもとの一にかへりて、つくることなし、またもとの初心にかへり、またもとにかへり、無量にして極りなき心に至る」のだ、というのである。
要すれば、鉄舟の剣法は、敵の好む処をよく見極め、敵の動きに随い、こちらが主導権をとって、敵の「切っ先」と「拳」に目をつけ、迷わず、間髪を容れず、無拍子の拍子で、心残さず、敵の「拳」を一刀両段に打ち据えよ、ということに尽きるといってよい。
実は、鉄舟の剣法は、後でお話しする、上泉伊勢守を流祖とする「柳生新陰流」の剣法「活人剣」(かつにんけん)そのものだったのである。鉄舟は生涯一度も、幕末の混乱のなかにあっても、刀で人を斬ったことはなかった。
山岡鉄舟のいう
「武士道」とは
では、鉄舟は、兵法の道である「武士道」を、どのように考えていたのか。
これが明らかになるのは、鉄舟が著した「武士道」( 万延元年(1860年)、鉄舟25歳 のとき)のなかの次の一文だ。
「 わが邦人に、一種微妙の通念あり。神道にあらず、儒道にあらず、仏道にもあらず、神。儒。仏。三道融和の通念にして、中古以降専ら武門に於て、其著しきを見る。鉄太郎之を名付て武士道と云ふ。然れども未だ曾て文書に認め、經に綴って伝ふるものあるを見ず。」
そして、鉄舟は、「武士道」を次のように定義する。
「 武士道は、(中略)善悪の理屈を知りたるのみにては武士道にあらず、善ありと知りたる上は、直に実行にあらわしくるをもって、武士道とは申すなり。」
そしてまた、
「武士道は、本来心(道理、すなわち天地の心理)を元として、形(行為)に発動するものなれば、形は時に従い、事に応じて変化変転極まりなきものなり」と。
すなわち、鉄舟は、「武士道」で大切なのは、起きている事の善悪を天地自然の道理に照らして判断する「判断力」だけではなく、その判断に基づき自分の目前で起きている事態の改善に向けて行動を起こす「決断力」の方にある。その行動は、これから起きる不測の事態に対して、常に「臨機応変」でなければならない、と考えたのである。
「必勝の剣法」
の二つの流れ
剣法の歴史をみると、戦国時代が終わった1600年の関ヶ原の戦いを境にして、「介者剣法」(鎧をつけた兵士の剣法)から、「素肌剣法」(甲冑を身につけない剣法)への大きな流れの転換がみられる。
すなわち、「殺人刀」(せつにんとう)の介者剣法から、「活人剣」(かつにんけん)の素肌剣法への移行だ。
「活人剣」の原形はすべて介者剣法の中にある。介者剣法から剣法のエッセンスを抽出したのが、「柳生新陰流」の上泉伊勢守であった。
介者剣法は、重たい兜を被り、鎧をまとって戦った戦国時代の剣法だ。甲冑での戦いは重たい兜や鎧を着けているため、重心を低くした「沈なる身」での斬り相いとなる。
この剣法の極意は、とにかく「相手の拳(こぶし)を斬ること」であった。なぜなら、甲冑から露出していて、こちらから一番近いところにあるのが、相手の拳であるからだ。
介者剣法では、「切っ先三寸」(太刀の先端から三寸、約9センチ)で、相手の長さ三寸ほどの拳を斬ることを「三寸二つ」と教えている。
さらに、相手の拳を斬るために、「十文字勝ち」をいう教えがある。たとえ敵がどのように打ってきても、敵と正対し、自らの《人中路》を、真っ直ぐ、一刀両段(新陰流では「断」ではなく、「段」という)に断つように斬ると、必ず敵の拳が斬れる、という教えだ。
人中路とは、自らの身体の中心を貫くラインのことだ。敵の人中路と、自らの人中路を合わせて、自らの人中路を断つように斬ると、切っ先三寸で相手の拳が斬れるのである。
介者剣法では、この刀法を「拳を見て拳に勝つ」と言い習わしてきた。
伊勢守の活人剣でも、やはり、自らの《人中路》のこの「十文字勝ち」が、剣法の「技」の根幹におかれている。
しかし、介者剣法の「理」の根元は「殺人刀」にある。殺人刀は、自分の得意とする技に磨きをかけて、その得意技を生かしてスピードとパワーで敵に勝つ、という考え方だ。
殺人刀の「殺人」(せつにん)とは文字通り、人を殺すという意味ではない。「殺」とはスピードとパワーで敵を威圧し、委縮させることをいう。
一対一の斬り相いは、相対する二つの存在の熾烈なぶつかり合いになるが、殺人刀で勝てるのは相手に対して自らの実力が勝っているときに限られる。
つまり、殺人刀では勝つチャンスもあれば、負けるリスクもある。勝敗がどちらに転ぶかは、実際に剣を交えるまでわからない。
しかし、江戸時代に入り、「大坂の役」を最後に大規模な合戦はなくなり、天下泰平の世となった。
ここで剣法は、「介者剣法」から「素肌剣法」へと大きくパラダイムシフトする。剣法の「理」が「殺人刀」から「活人剣」に変わったのである。
活人剣は、殺人刀の「殺」が、敵を威圧してその働きを殺す意味だとしたら、活人剣の「活」は、敵を働かせて、敵の働きを利用して、それに対応して勝ちを得る、という柔軟な考え方をとる。この考え方を突きつめていくと、自分と敵の関係を見極めて、自分と敵を共に生かす、という生き方につながっていく。
敵を先に働かせて、そのスピードとパワーに応じて、無形の位から自由闊達に剣をふるって勝つ。相手は「斬った」と思っているのに、いつの間にか斬られている。これが活人剣が想定するところの《必勝の方程式》だ。
実は、武士道は、「殺人刀」の介者剣法から「活人剣」の素肌剣法への移行期に、そもそも、剣法の「普遍的価値」とは何なのか───さらにいえば、権力を握りこの世の中を統治する《武士》という支配者階級に求められる「真実の道」とは何なのか───という重い課題を、真摯に追求するところからはじまったのである。
すなわち、《武士道》とは、人間の生き方の、兵法における「真実の道」を発見することだったのだ。
「真実の道」は、何も兵法にだけあるのではない。それは、およそ技術をもち、道具を用いて生きていく、あらゆる「人間」と「人間」の間に無数に存在する《 間合い=「時間」と「空間」 》において、極めて有効に作用しているところの語りがたき「理外の理」の働きなのである。
だから、武士道は、人間の《観念》のうちにあるのではなく、人間の有効な《行為》のなかにある。
しかし、有効な行為の理論は、あまりに精妙で、これを観念によって極めることが不可能であることから、人は器用・不器用などという曖昧な《言葉》で済ませようとする。
これを曖昧にせず、《器用》という言葉の中に含まれる「理外の理」を突きつめること、これがまさに《武士道》だったのである。
「上泉伊勢守」
と「宮本武蔵」
この「介者剣法」から「素肌剣法」への移行期にあらわれたのが、柳生新陰流の流祖・上泉伊勢守と、宮本武蔵だった。
伊勢守は室町時代末期の1508年頃生まれ、戦国時代の真っただ中を生き、75歳ほどで死んでいる。武蔵は、本能寺の変があった天正10年(1582年)、ちょうど伊勢守が死んだ頃に生まれ、1645年の乱世が収束した時代に死んでいる。
面白いことに、「活人剣」の創始者である伊勢守と入れ代るかたちで、最後の「殺人刀」最強の剣客であった武蔵が生まれてきたことだ。
伊勢守の偉大なところは、戦国期のある特異な時点において、その時期に形成された新当流(神道流)、念流、陰流の3つの流れを修め、なかでも陰流を最も重んじ、それに自らの工夫を加えて、「新陰流」という新しい「活人剣」の流儀を創造したことだ。
伊勢守の「活人剣」の奥義は、伊勢守が著した秘伝書『影目録』(全四巻)の『燕飛』の巻に収められている。
また、武蔵の剣法は、武蔵が死ぬ2年前の寛永20年(1643年)に書いた『五輪書』によって知ることができる。
これを読むと明らかになるのは、両者の間に、剣法の「技」においては、寸分の優劣の差はなかったが、剣法の「理」において、両者の間に根本的な理解の差があった、ということだ。
それは、「技」において優劣の差のない、相対峙する2つの存在が、〝いのち〞をかけて対決する「斬り相い空間」において、相対峙する2つの別々の太刀の、それぞれの回転運動を貫くところの「理」の違い──── つまり、2つの太刀のそれぞれに働く運動力学の違いをどう理解していたのか───という問題だ。
武蔵の「殺人刀」では、太刀の運動力学の視点がまったく欠落しているのだ。
「斬り相い空間」は、マトリクスで示すと、「空間軸」と「時間軸」の合成空間だ。「自分」の立ち位置は、両軸の交点0の空間軸上にある。相対峙する「相手」の立ち位置は、自分からみると時間軸上の《時間空間》のなかにある。
運動力学の理論に従えば、太刀に同じ力が加えられたとしても、太刀の回転速度(スピード)は、時間軸上よりも、空間軸上の方が、回転スピードが速い。
つまり、空間軸上にいる「自分」の太刀の方が、時間軸上にいる「相手」の太刀よりも、斬り下ろす太刀のスピードが速い。「自分」は、常に相対優位のポジションにいるので、十分注意深く、かつ、臨機に対応できれば、「自分」は自然の理によって守られているのだ。
伊勢守が「活人剣」を編み出したのは、「空間軸」と「時間軸」の隙間にある、この「理」に気がついたからではなかったのか。
彼は、これを「理外の理」というかたちで認識し、どうも「空間」と「時間」の関係を相対的なものとみていた節があるのだ。
現代物理学の立場から言えば、伊勢守はアインシュタインの「相対性理論」の力学に立っていたのである。これに対して、武蔵には時間軸が存在しない。彼は、ニュートン力学の立場に立っていたのだ。
柳生新陰流の
剣法の「奥義」
柳生新陰流剣法の「奥義」とは何か。
柳生新陰流を他流と隔てている柳生新陰流の奥義は、「性自然」と「転」(まろばし)という2つの理念を剣法の要においたことにある。
一、「性自然」
剣術では、心と身体、身体と太刀を自然と一体化させて、バランスよく動くことが理想だ。ところが人間は相手を斬りたいと気がはやると身体と太刀、手と足がバラバラになりがちだ。なまじ手が器用なため、手先のみに頼って相手を斬ろうとしたり、手が先に出て足が残ったりする。それでは自然の摂理から離れてしまう。
新陰流では、「性自然」の状態を、「刀身一如」とか「心身一如」、また、「刀中蔵」、「神妙剣」あるいは「無刀取り」と教えている。
「刀身一如」とは、太刀という道具と自分を一体化すること、「心身一如」とは、自分の心と身体を一つにすること、「刀中蔵」とは、相手から見たときに自分の身体を構えた太刀に隠す、という意味だ。
「神妙剣」とは、「人知を超えた剣」という意味で、ありのままで滞りなく、怒りや怖れといった感情に左右されない純粋な心こそが、敵の千変万化の働きに対して自在に応じる太刀捌きの原動力になる、という教えだ。
また、「無刀取り」とは、太刀を持って向かってくる相手に対して、太刀を持たない無刀の状態で立ち向かい、相手の太刀を奪って勝つ技だ。しかし、抜刀した相手に素手で立ち向かい、その太刀を奪取するのが無刀取りの目的ではない。
太刀を持たない無刀のときに、人ははじめて太刀を持つ人の気持ちになれる。そのとき、本当に自分と敵が「自他一如」の状態になる。そうなると、必要以上に焦ったり、不利に思ったりせず、敵の気持ちになって、敵が斬りやすいように誘い出し、敵に斬り込ませて、これに対応することができる。
無刀という究極のシミュレーションを介して、真剣勝負の本質を知ることができる、と教えるのだ。
二、「転」(まろばし)
流祖・伊勢守は、先にあげた秘伝書『影目録』のなかで、「転」(まろばし)の極意を、次のように説明している。
「‥‥‥懸待表裏は、一隅を守らず。敵に随って転変して一重の手段を施すこと、恰も
風を見て帆を使い、兎を見て鷹を放つが如し。懸、懸に非ず。待、待に非ず。懸は意待に在り。待は意懸に在り。‥‥‥‥」
ここに出てくる、「懸待表裏」とは、相手との「斬り相い空間」を構成する重要な4つの要素のことだ。
「懸」とは、先制攻撃を行うこと、「待」とは、敵の攻撃を待つこと、「表」とは、敵が構えた太刀の刃の方向あるいは前の方向から攻めること、「裏」とは、それとは逆に敵の構えた太刀の刃の裏から攻めること。また、「一隅を守らず」とは、いずれにもこだわらず、の意味だ。
そして、伊勢守は、「転」とは、この「懸待表裏」の4つのいずれにもこだわらず、相手の出方に応じて柔軟に対応することなのだ、という。
これは、水夫が潮風を見て船の帆を操り、猟師が兎の動きを見て鷹を放つのと同じで、攻めることは攻めることではない、守ることは守ることではない。攻めることは守ることであり、守ることは攻めることなのだと、伊勢守は看破したのである。
柳生新陰流の「活人剣」は、この「性自然」と「転」という2つの理念を要においている。
では、ここで新陰流「活人剣」の奥義を整理しておこう。
新陰流の「活人剣」は、相対する2つの存在がぶつかり合う「斬り相い空間」において、まず、「相手」と「自分」の関係を見極め、「相手」を先に働かせて、相手の「転」(まろばし)を活かして、これを活用するかたちで、「一瞬の時間差」を利用して、後から「相手」に打ちかかり、迷わず、自らの《 人中路 》(自らの身体の中心を貫くライン)を真っ直ぐ、一刀両段に、斬り下ろせば、「相手」の太刀の上に乗るかたちで、必ず勝ちを治めることができる、というものだ。
一言でいえば、《 「後手必勝」の剣法 》ということができる。
要するに、活人剣においては、こちらのシナリオに沿って相手を動かし、斬り相う前から、こちらが主導権をとり、相手が「勝てる」と思ってどう斬ってくるかを予測して、待ち構えて、これに打ち勝つのである。
柳生新陰流剣法の
「後手必勝」の数理
では、後から打ってなぜ勝てるのか。
新陰流の剣法では、先に働かせ斬ってきた相手に対し、後から打ちかかって、相手の太刀に乗って勝つ、という。普通に考えると、先に動いた方が有利で、それを見てあとから動くと、この「一瞬の時間差」で斬られてしまうはずだ。
実は、「斬り相い空間」における、このほんの僅かな「一瞬の時間差」に、新陰流秘伝の「後手必勝」の数理が働くのである。
(事務局からお詫び)
(数式部分が正しく表示できないため、該当部分をスキャンして掲載いたしました。見難いとは存じますがよろしくお願いいたします)
「生きる」とは
どういうことか
生きものが「生きる」ということは、このe(時間軸)とπ(パイ・空間軸)の回転スピードの「一瞬の時間差」を利用して、「自分」のいのちを、「敵」から守ることなのだ。
生き続けるには、《3つの条件》を満たす必要がある。
1、敵の「転」を観て、その働きを予測する。
2、敵の「転」に、臨機応変に応じ、その働きを封じる。
3、そのためには、普段の「習い」「稽古」「工夫」を欠かさない。
「生きる」こととは、生存価値の善・悪・正・邪以前に、この世の自然の摂理に従うことであり、生きる価値は、生き続けること自体にある。
野生のライオンはシマウマを食べて生きている。追われるシマウマは、ライオンから、15%の時間軸上のハンディキャップを使って逃げ切ることにより、食われない確率が五分五分になる。だから、シマウマは絶滅しない。
生きものが自らの生存リスクを察知して、十分注意深かければ、この世の中で生き続けられる理由が、まさにここにあるのだ。
以 上
この内容についてお問い合わせは北川宏廸氏hirom-ki@js4.so-net.ne.jp
又は山岡鉄舟研究会info@tessyuu.jpにお願いいたします。
(参考文献)
1、「英傑 巨人を語る」(勝海舟/評論、高橋泥舟/校閲、安部正人/編、日本出版放送企画発行、1990年)
2、「負けない奥義───柳生新陰流宗家が教える最強の心身術」(柳生耕一平厳信著、ソフトバンク新書161、2011年)
3、「五輪書」(宮本武蔵著、佐藤正英 校注・訳、ちくま学芸文庫、2009年)
4、「宮本武蔵 剣と思想」(前田英樹著、ちくま文庫、2009年)
5、「博士の愛した数式」(小川洋子著、新潮文庫、2005年)
2011年10月12日
駿府・静岡での鉄舟・・・其の二
山岡鉄舟研究
駿府・静岡での鉄舟・・・其の二
江戸から駿府への徳川家臣団移住は、慶応四年(1868)から明治元年へと、新しい年号に変わった十月、この一ヶ月で全員の移住を完了させよと命令が新政府からなされていた。しかし、十月二日から十二日まで明治天皇の東上、その間は徳川家移住が中止、また、家屋・家具等の整理処分に時間がかかり、実務的に一カ月では無理で、陸路は翌年まで続き、海路は十月と十一月の二カ月にかけて行われた。
移住に陸路と海路のどちらを選ぶかはお金次第であった。お金のある者は陸路、または個人で船を雇った。この雇船は商いのため江戸に立ち寄る帆前船を清水港までチャーターしたもので、お金がない者は徳川家がチャーターした大型船での移住となった。
この移住の状況、今の時代につながることも多いので、当時の記録からいくつかみてみたい。最初は陸路。それを幕末時に御徒(おかち)であった山本*政(まさ)恒(ひろ)(七十俵五人扶持)の日記からひろってみる。
御徒とは徒士・歩行とも書き、御目見以下の軽格武士御家人で、職掌は将軍近辺の警護である。この日記は原題を「政恒一代記」、それが「幕末下級武士の記録」(昭和六十年・時事通信社)として出版され、この中に東京出立前の家屋敷処分状況が記されている。
「無禄移住を願出たり。因て江戸持地面は其儘上地し、家屋は売方多く買い手少なきを格外の下落也。三年前に建直し、瓦家にて建坪二十余坪の家作、漸くにて代金弐拾円にて売渡」
政恒の住所は下谷三枚橋通仲御徒町大縄地(現・JR御徒町駅近辺)で約二百坪の敷地、政恒は多少絵心があり、自宅を絵図で遺している。これを見ると池があり築山もあって庭木も大きい。これを移住までに「悉く焚木に使用した」と記しているが、現代では豪邸となる立派な邸宅が、江戸時代の軽格武士御家人の住むところであった。
今の御徒町あたりは雑然と建て込んでいる街並みであるが、古地図を見れば御徒屋敷が整然と区画され並んでいる。
この当時の江戸は、素晴らしい調和のとれた景観都市であった。それを証明するのがイギリス人写真家「フェリックス・ベアト」の写真である。撮影したのは慶応元年(1865)から2年(1866)頃で、江戸市中をパノラマ写真として残している。特に海舟と西郷が江戸無血開城を談じた愛宕山から撮影した江戸景観は見事である。今、愛宕山から眺めると、当時の景観は望むべくもなく、ベアトと同じ位置から見た現代の東京の街並み、それに貧しさと哀れさを感じる。
このような無秩序景観になっていった始まりが、徳川家臣の駿府移住という要因から発生したと推測される。家臣の家屋が一斉に売りに出され、不動産市場の需給バランスが一気に崩れ、売り手不利で安く買いたたかれ、それを購入した江戸市民は、時間経過の中で何度か転売しつつ、その度に土地は細かく区分所有されていき、都市景観の調和美が失われていった、と政恒日記から推測され、東京の現状を成程と思った次第である。
更に、政恒に日記から移住の途中状況を見てみたい。
「明治二年(二十九歳)正月家族引纏め東京出立、川崎・藤沢・小田原・三嶋・吉原・由井・江尻の七宿へ泊し、駿府研屋町米商山本屋吉右衛門方に止宿す。予の家族は、かん・よし(七歳)・万平(五歳)・文次郎(二歳)さだ都合六人なり。因て元大御番京都へ在勤の時用ひし長持の駕籠を求め、夫へ夜具・蒲団三組を敷入れ、子供三人を乗せ、屋根へは下駄・傘・おまる等を乗せ、其他の者は歩行し、足の労れし時は駕籠を雇ひし也」
家族六人が七泊もして荷物を持って陸上を徒歩で移動したのであるから、随分お金がかかったであろう。現代の引っ越しからは考えられない状況である。
移住では家族間の悲劇も発生した。四百俵の平賀家の事例である。(「徳川家臣団第三編」前田匡一郎著)
「内匠(勝成)の妻は三枝左兵衛の娘で左兵衛が朝臣(新政府)になったので、父も内匠も大層立腹して、三百年来の徳川家の御恩を忘れたる不忠不義の武士のこんな娘は我が家には置けぬと早速離縁を申渡し、妻は女の子の幸を連れて泣く泣く三枝家へ帰った」
徳川家が禄高七〇万石では従来の生活ができないのであるから、朝廷・新政府へ仕えるよう強く勧奨し、それを受け入れた結果は夫婦別れという悲劇を生みだしたのだ。
さて、海路であるが、これについては大正十五年(1926)静岡民友新聞に「府中より静岡へ」という記事が坂井闡(せん)という人物により連載され、その中にチャーター船の様子を述べた明治三十四年の
「塚原渋柿園」(明治期の小説家)による回想が紹介されている。(「徳川慶喜静岡の三十年」前林孝一郎著 静岡新聞社)
「移住者を清水湊まで運んだのはアメリカの『飛脚船』ゴールデン・エージ号という船であった。長さは七十~八十間(約二百五十~二百九十メートル)、幅十二~十三間(約四十五メートルほど)の大船で品川沖の台場付近に停泊していた。乗船希望者は本願寺あるいはその付近の民家を借りて待機していたがその数は約二千五百から二千六百人に上がっていた。
むろん、その中には婦人や子供、一人では動けない老人なども含まれていた。当然のことながら持ち込み荷物は最小限に制限されていたが、みな新生活への不安から一品でも多く持ち込もうとして必死だった。出発当日は朝早くから数十隻の小船が動員された。小船は陸と船を数百回も往復したが、乗り組みがすべて完了したのは夕方六時を回っていた。
船はパンク状態で甲板はテントを張って『野営』の状態、船内も『すしを詰めたというより目刺し鰯を並べた』ような状態だったという。約二里(八キロメートル)も小船に揺られたうえに、貨物船特有の石炭のにおいにやられて船内あちこちで嘔吐するものが出た。病人の呻き声、子供の泣き声、そしてそれをなじる水夫の怒鳴り声で、船内は『牢屋どころか地獄』を思わせる様相であった。
特に困ったのは用便であった。これだけの人数に対応するだけのトイレのあろうはずもなく、船底に四斗樽を十四、五も並べて代用した。しかし男性はともかくとして女性はと言えば元旗本・御家人の奥様、お嬢様たちである。たいそうな難儀をしたが、偶然にも船内に持ち込まれていた『おまる』が引っ張り凧になった。
また樽にたまった汚物を船外に捨てようと樽を吊り上げたが、途中で綱が切れ、乗客がこれを頭から浴びるなどというハプニングも起こった。二日半かかって清水湊に到着したが、この間亡くなった人は四、五人、出産も五、六件あった」
このような塚原の回想内容は、その後各文献でしばしば引用され、一般的にこれが海路移住の全てであったかのように伝わっている。これは大変な誤解であることを指摘したい。
外国船による大量輸送は九回行われた。これは東京都立公文書館の資料により概略確認できる。(徳川家臣団第三編)
1. 十月二日 横浜亜国商人所持蒸気飛脚船ニーヨルク 千三百八十八人
2. 十月八日 オーサカ 千四百八十一人
3. 十月十一日 アテレイン 四百十一人
4. 十月十五日 アテレイン帆前船キングフィルツリプテ 千七百五十人
5. 十月二十四日 ヤンシー 二千二十八人
6. 十月二十八日 ヤンシー 千八百九十三人
7. 十一月三日 クルリュー 四百八十四人
8. 十一月五日 ヤンシー 千四十七人
9. 十一月九日 ヤンシー 八百十四人
合計 九便 一万千二百九十六人
この便船の区分けは、基本的に百俵以上(御目見)と未満(御家人)に分けたようであるが、これは当初の基本方針であって、実際は様々に乗船したらしい。
なお、上の九便リストに塚原が回想したゴールデン・エージ号が見当たらない。本人の記憶違いと思われるが、人数の多さから推察して十月二十四日五便のヤンシーではないかと考えられる。
次に、十一月五日のヤンシー千四十六人に乗船した新庄萬之助直義の記録を紹介したい。新庄は両番格(御小姓と御書院の両番を勤め得る家格)の四百石であるが、母と妹を残し、父と二人で駿府に移住するため本願寺に入った。(徳川家臣団第五編)
「此院にて長崎人にて何某作太郎とて御雇外国船の通訳をなす者に逢ひけり。其者の言に自分は少し病気にて爰(ここ)に居残り居るが、自分の乗り居るヤンシューと云える船は雇船中最大なるものゆえ其船に乗る方船暈(めまい)に罹る事少なからんとの事に他の船の出るにも係らず其船の来るを待ち、十一月五日ヤンシューに乗込、作太郎周旋にて上等の一室を借り受けたり。
船長の名をバチラと云ひ支那人のボーイ多く徘徊しチュデヤートと云ふ語を盛に誦す。其何を意たるを解する能はず。船中は板壁塗料及石炭の匂ひにて人々頭痛を感ず。父は之が為に炊出しの握飯を喰ひ得ざりしが余は別条なかりし。船は日没後に出帆し、日出前清水港に着す。軈(やが)て日出れば三保の松原は近くして緑に富士山は遠くして白し、其外見馴れぬ山海の景色に少しは紛るる事を得たり。是れ実に十一月六日の朝なりき」
このように一日で順調に海路移住した事例も記録に見られる。事実は様々な角度から検討しないといけないと思う。
一方、受け入れる駿府の住民には町触れが出されていた。
「このたび約千人ほどが東京を出発した。そのうちに当地へも到着することになるが、各町内で宿泊場所を提供してほしい。見苦しい住居でも構わないということである。到着次第、各町内へ宿割りをするので、不都合が生じないように取り計らって欲しい」
清水港に到着した移住者は、とりあえず近在の民家や寺院の本堂を借りて住みつくことになったが、彼らは「お泊まりさん」と呼ばれた。
駿府には六百九十四人、浜松七百二十一人、掛川七百一人、遠州横須賀六百八十二人、田中六百五十人、相良七百六十人、中泉七百二十九人、小島三百九十九人、三州赤坂六百二十八人、三州横須賀六百六人。いずれも一家の当主の人数である。一家五人と想定し従者も考慮に入れると、駿府周辺には約五千の人口流入があったと考えられる。
当時の駿府の戸数は四千四百七十六戸、人口は二万千四百六十六人であるから、四分の一に当たる人口の流入があったわけで、急激な人口増加であった。
先に触れた塚原の親は元二百三十俵取りの与力で、江戸市ヶ谷に四百余坪、大小合わせて十一間という屋敷を構えていた。
しかし、移住後、両親が清水に確保できた家は六畳に三畳の二間、三尺四方の台所に竈が一つ、天井はなく屋根は板葺で、半分は朽ちていた。これでも「壊れた厩に住んでいる人たちに比べればましなほう」と母親が語っていたという。
それでも屋根さえあれば雨露はしのげたが、問題は食糧の確保である。無禄移住という無収入を承知で覚悟してきたのであるから藩は養う義務はない。しかし、藩も見るに見かねて、暮れの十二月に無禄移住者に扶持米を支給することにした。
三千石以上の家臣に毎月五人扶持、これが最高扶持で最低は毎月一人扶持であった。一人扶持とは玄米一斗五升支給で、白米にして一割減であるから一日四合ほどになる。これは一家に支給される量であるから、家族の人数を考えればとても足りない。食糧が尽きて一家七人が餓死したとか、村人が哀れんで麦粥を与えたところ、一気に数杯も平らげたあげく、にわかに苦しみ息絶えたというような話が伝えられている。
瀬名村の農家に間借りした市田家は元千二百石、その子剣三郎が山に入り、たまたま椎茸の栽培地に入り込み、椎茸を思わず袂に入れたところを「泥棒」と連呼され、かっとなって刀を抜いて農民を切ってしまった。この事実を自供した剣三郎を藩庁も許すわけにいかず切腹となった。剣三郎は十九歳であった。
このような悲劇は数限りなくあるが、六十五年前の戦後、日本国民の多くは同様の食糧難に陥った。この時、筆者は田舎で親と一緒に山や川の土手で食べられる物を漁った経験があるので、徳川家臣の駿府移住は他人事ではなく感じ、深く身につまされる。
だが、全員が困ったわけでなく、地元の経済活況に関わった事例もある。静岡市伝馬町はJR静岡駅近くで、江戸時代は参勤交代の宿場町として旅人で賑っていた。しかし、幕末になってさびれる一方であった。ここに隣の鷹匠町に「お泊まりさん」が入って来た。
このお泊まりさんは貧乏幕臣とは違って、邸を与えられたそれなりの身分の者たちであった。そこで、伝馬町は町の繁栄を協議して遊郭をつくることを藩庁に届け出た。慶応四年六月のことであるから、お泊まりさんがまだ実際に移住してこないタイミングであって、如何に伝馬町はお泊まりさんに期待したことが分かる。結果は、その後芝居小屋や湯屋もでき、旅籠屋は遊女屋に代わって繁栄した。
これは戦後の進駐軍目当ての同様商売で荒稼ぎしたものと重なるが、いずれにしても一概に悲劇ばかりではなかったということを認識したい。
ところで、山本政恒のその後であるが、
「家族を伴って浜松に移住、浜松奉行井上八郎の配下に入った。やがて払い下げ金を得て、裏早馬町に敷地およそ六百坪、建坪五十坪の家屋を購入することができた。当初は、藩から『役持』(手当て金)が唯一の収入であったが、これだけでは生活できないので、屋敷内の掃除にために雇い入れた農民に農作業を教わり、耕した農地から相当の収入を得ることができるようになったという。
明治五年(1872)十月、浜松県監獄の下級役人、のち捕亡吏(警察官に相当)となったが、二年後、自分の不注意から囚人を取り逃がし、免職となってしまった。その後は張り子面作りの内職で生活せざるを得なかったが、職を得るため単身上京、翌年四月に印書局取片付け方として、さらに五月に熊谷県に職を得てやっと安定した生活を送れるようになったのだった。下級役人または警察官となるというのが、無禄移住した旧幕臣のたどった平均的なコースであった」(「徳川慶喜静岡の三十年」)
ところで、この静岡移転に伴い、徳川家臣は以下の四つに分けられたことは前号で述べた。第一は脱走して反政府活動に走った者、第二は朝廷・新政府に仕える者、第三は暇乞いして農工商になる者、第四は藩臣として無禄でも徳川家に残る者である。
この身の振り方から指摘できるのは藩側からの「リストラ」が行われなかったことである。現在の日本、企業経営が厳しくなると社員の首切りリストラが、まず、最初に行われることが多くなっている。しかし、徳川藩は70万石に合わせるような家臣の首切りは行わなかった。駿府に来る者は全員受け入れている。
これは関ヶ原の合戦後、西軍だった上杉家が会津から米沢への四分の一に減封され、その際「リストラ」は一切しなかったこと、それが平成22年のNHK大河ドラマ「天地人」主人公直江兼続によって語られたことは記憶に新しいが、これより過酷な実質四百万石から七十万石へと八割以上の減封であった徳川藩が、家臣の「リストラ」を実施しなかったことを高く評価したい。
徳川藩は武士道経営を貫いたと理解し、このような政策を決定し実行した藩経営に鉄舟が参画していたことを再認識したい。
鉄舟は慶応四年・明治元年に幹事役として海舟と二人で名前を並べ、同年九月には権大参事の藩政補翼となり、徳川から静岡藩となった政治に重要な役割を負う立場に栄進していた。


