« 2011年11月 | メイン | 2012年01月 »
2011年12月30日
2012年1月例会ご案内
2012年1月例会は以下のように開催いたします。
開催日 2012年1月18日(水)
場所 東京文化会館第一中会議室
時間 18:30から20:00
発表者 岡村紀男氏と山本紀久雄が担当いたします
①岡村紀男氏
ご発表は「ほっとスペースじいちゃんち」です。
岡村紀男氏は昨年6月、自宅を子育て広場に開放し「ほっとスペースじいちゃんち」の名で週1回、乳幼児連れの親子を招き交流できる場所を提供しておられます。 区民講座で知り合った元保育士の女性らもスタッフに加わり、育児相談もあり、これまでに110組以上の親子がじいちゃんちを訪ねられています。
岡村氏は大学の就職課で学生の就活支援をしてきた経験から、幼い頃の家庭環境がその後の人間形成に大きな影響を与えることを痛感、今の子育て環境を憂慮し「昔は地域で子育てをしたが、今はそのような仕組みが薄まり、親が気軽に相談できる場がない。そういう場を提供したい」という戦略目標を持って実行されています。
鉄舟の生き方から、今の時代の生き方を学ぶ我々にとって、このような「生き方」を選択され実行している岡村氏から学ぶことは大きいと思います。
なお、日経新聞2011年10月26日(夕刊)「高齢者男性が子育て支援」記事に岡村氏が登場しておりますのでご参考ください。
②山本紀久雄
2011年は日本にとって稀なる事件の連続で厳しい一年でしたが、新しい年は期待できると思います。まずはその根拠について考察いたします。
鉄舟研究は、明治天皇がその治世期間である、15歳から61歳までの46年間を通じ「偉大な天皇」として、日本を世界歴史の一ページに登場させた業績は誰もが否定できない事実であり、鉄舟が明治天皇の侍従として、明治天皇治世に貢献したことも事実です。
しかし、鉄舟という武士階級出身者が天皇の身近に仕える侍従になるには、前提として廃藩置県に匹敵する「宮廷改革」が必要でした。
その改革までのプロセスと、西郷隆盛と鉄舟の両者がどのように対応していたかについて考察いたします。
3.2012年2月例会は以下のように開催いたします。
開催日 2012年2月15日(水)
場所 東京文化会館第一中会議室
時間 18:30から20:00
発表者 山本紀久雄が担当いたします
4.2012年3月例会事前ご案内
3月17日(土)18日(日)に新潟県阿賀野市出湯(でゆ)温泉で一泊合宿例会を行います。12町歩の山麓に位置する川上貞雄様邸にて開催、鉄舟、海舟、西郷、伊藤博文、山県有朋、土方歳三等の書と、吉田松陰と関わる佐久間象山の直筆手紙を拝見し、隣接する日本の秘湯「清廣館」に宿泊いたします。
後日、改めて詳しくご案内をいたしますので、皆様、楽しみにお待ち願います。
5.東日本大震災義援金
既に申し上げておりましたように、東日本大震災義援金として、3月以降開催いたしました例会の参加費から会場費等の実費を差し引いた10万円を、12月27日NHKさいたま放送局を通じて寄付いたしましたのでご報告いたします。
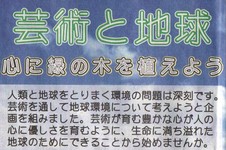
皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
以上
2011年12月開催結果
2011年12月開催結果をご案内します
①末松正二氏の発表
11月に続く終戦工作を資料に基づき発表がありました。
昭和20年8月14日10:00皇居防空豪で御前会議が開かれ、そこで昭和天皇が次の発言をされ、戦争終結の聖断が下されました。
「外に意見が無ければ私の考えを述べる。反対論の意見はそれぞれ聞いたが、私の考えは前に申したことに変わりは無い。私は世界の現状と国内の事情とを充分検討した結果、これ以上戦争を続けることは無理だと考える。
国体についていろいろ疑義があるとのことであるが、私はこの回答文の文意を通じて先方は相当な好意を持っているものと解釈する。先方の態度に一抹の不安があるというのも一応は最もだが私はそう疑いたくない。要は我が国民全体の信念と覚悟の問題であると思うから、この際、先方の申し入れを受託してよろしいと考える。
どうか皆もそう考えて貰いたい。(中略)この上戦争を続けては結局我が邦が全く焦土となり万民にこれ以上苦悩を嘗めさせることは私としては実に忍びがたい。
祖宗の霊にお応え出来ない。素より先方の遣り方に全幅の信頼を置き難いのは当然であるが、日本が全く無くなるという結果に比べて、少しでも種子が残りさえすれば、さらにまた復興という光明も考えられる。
私は明治大帝が涙をのんで思い切られたる三国干渉当時の御苦衷を忍び、この際耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、一致協力して将来の回復に立ち直りたいと思う」(以下続くが省略)
この内容をお聞きし、改めて日本は天皇中心国家であると確認し、その後の歴史が昭和天皇ご聖断は妥当であったとことを証明しています。
また、日本は天皇判断で国体の戦略決定がなされているという最適例であり、世界で稀なる天皇制の日本は恵まれていると感じた次第です。
末松氏のご発表から学ぶ点が多き12月例会で、末松氏に感謝申し上げます。
②山本紀久雄の発表
「鉄舟が明治天皇侍従となる前提を理解したい」というテーマで発表いたしました。
鉄舟は、明治天皇侍従として、天皇が二十歳から三十歳になられるまでの、人間形成時期として最も大事な年齢時に仕えました。
しかし、当時の状況を考えると武士階級出身の一般民間人が、簡単に侍従として仕えられたのかという疑問が浮かびます。
その事例として、明治天皇即位時の各国公使謁見に対する宮廷内の反対事件を取り上げ、公家以外の一般人が侍従という立場にはなれることなどありえなかった慣習の塊、これを破壊しなければ鉄舟の登場もなかったことに触れました。
なお、改革推進には必ず賛成と反対があって、それは両者の外国との接し方の痛み度合いによるものだということを、明治維新改革と現在二派に分かれて論議されているTPP問題を事例として取り上げ解説いたしました。
加えて、アメリカのNYとSFの武道家と11月に出会い、外国の武道家が武道指導する際に、新渡戸稲造以外の英文武士道本を求めている実態についても報告いたしました。
2011年12月23日
痩我慢の説と鉄舟・・・その一
痩我慢の説と鉄舟・・・その一
山岡鉄舟研究家 山本紀久雄
福沢諭吉は明治二十四年(1891)、「痩我慢の説」で勝海舟と榎本武揚を正面切って批判した。徳川幕府と明治政府の両方に要人として仕えたことへの士道・士魂からの批判である。だが、鉄舟も同様に明治天皇の侍従として仕えたが、福沢から批判されなかった。それらの背景について今号以下で検討してみたい。
さて、この検討に入る前、鉄舟の長女である松子女史に、鉄舟の駿府での住居について直接確認している牛山栄治氏の記述を紹介したい。(「定本山岡鉄舟」新人物往来社)
牛山栄治氏は鉄舟の高弟である小倉鉄樹の薫陶を受けた人物である。
「私は鉄舟の長女である松子女史から直接きいたことがある。松子さんは文久二年(1862)正月十二日生まれであるから、明治二年には数え年八歳でよく覚えていられた。
『静岡に来てからの住居は材木町で、旧幕時代十分一と呼ばれた安倍川の岸にあった大きな徴税の役所を買いとったもので、洪水のときなど家の下まで水がおしよせて来たのを覚えています』
といっていた。
明治五年に『壬申戸籍』(注:編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と呼び慣わす)と言われる新たな戸籍が出来ているが、このときの鉄舟の住居は、駿河国安倍郡安西方七番屋敷となっているから、これは松子女史の話の通り、いまの材木町あたりを言っているのであろう。
このあたりは賤機山(しずはたやま)公園の西に隣接している静岡の中心地に近く、荒れ川で有名な安倍川に近いので、洪水には水もおしよせたであろうが、鉄舟屋敷は静岡藩では重要位置にあったのである。敷地は広大で、現在の井宮町六番地の赤石製材株式会社や疋田ガソリンスタンドの位置、水道町一番地の佐藤電気商会の位置にもおよぶといい、そこに『鉄舟屋敷跡』という碑が建っている。(注:この碑は老朽化し撤去されたままになっていたが、2010年四月に新しい記念碑が、静岡・山岡鉄舟会と地元の水道町町内会によって静岡市葵区水道町1-4に建立された)
ここで鉄舟はどんな家族といっしょに住んでいたのであろうか。壬申戸籍によると、養父山岡信吉一家がいる。信吉は天保三年(1832)七月二十日生れで、山岡静山の弟であり、高橋泥舟の兄で、鉄舟より四歳年長であるが、生来の唖であったので一応静山の家督はついだものの、鉄舟を養子に迎えたのであるから、鉄舟の養父となっていたのである。
鉄舟の家族としては、夫人英子(天保十一年四月九日生)と、長女松子、長男直記(慶応元年二月二日生)、二男静造(明治三年五月四日生)、三女しま(明治七年四月八日生)、四女多以(明治八年五月十一日生)が戸籍にはのっている。三女、四女は鉄舟が東京に出てから生まれたのでここに住んでいたのではない」
もう一つ面白い記述がある。牛山栄治氏は第二次世界大戦時の極東国際軍事裁判、東京裁判ともいうが、この裁判で日本側の弁護人に、ジョージ・ヤマオカという日系米人がいたが、これが鉄舟の曾孫であったという。(「定本山岡鉄舟」新人物往来社)
「鉄舟屋敷には、日本の石油開発の創始者になった石坂周造が、明治三年に第三回目の入獄から出牢して身を寄せ鉄舟の付籍となっていたが、鉄舟夫人英子の妹圭子を後妻にしたのでこの石坂夫婦が同居している。
この石坂には、嘉永五年三月二日に先妻との間に生まれた長男宗之助がいたが、この宗之助を鉄舟は長女松子の婿養子にして同居し、これが東京に出てから明治十六年十一月二十六日に長女まさと、明治十九年一月十四日に長男英一を生んでいる。
宗之助は温順な人柄であるが、石坂が石油会社を創立すると、八年間もアメリカのペンシルヴァニア州に留学させられ、石油採掘と精製について研究し、帰朝してからは鉄舟の養子になり、不振な石坂の石油事業にまきこまれて苦労していたが、鉄舟が死んだ明治二十一年に鉄舟の後を追うように死んでいる。
このとき長男英一は三歳になったばかりであったが、米国の知人が養育を引きうけてアメリカに連れていった。
英一はその後時計商として成功したというが、いつとはなく山岡家とは音信が絶えていた。大東亜戦が終わった後の、昭和二十一年五月三日から東京市ヶ谷台の旧陸軍省大講堂に、国際法廷が設けられて、東条英機元首相以下、A級戦争犯罪人二十八被告の極東国際裁判が開かれた。
この裁判は勝者が敗者を裁くという無理な裁判で、日本側の弁護人清瀬一郎など悲壮な努力をつづけていたが、この日本側の弁護人の中に、日系米人で、ジョージ・ヤマオカという人がいた。名刺には日本名で山岡譲治と添え書きがしてあった。
昭和二十二年七月十九日の鉄舟忌に、筆者は谷中全生庵の法要に出てこのジョージ・山岡に紹介された。彼は当時丸の内中通り、成富弁護士の事務所を借りていたがフランス人を妻にもち、その日も可愛い金髪の少女を連れていた。
このジョージ・山岡が山岡英一の子供であると鉄舟研究家の安部正人が断定してつれてきたのであるが、当人は親の家は元静岡県士族であるくらいの知識しかなく、鉄舟の曾孫であると言われてもあまり感激もない様子だったが、それでも当時としては大金の金二十万円を全生庵に寄進し、また千葉県勝浦に住んでいた鉄舟孫の龍雄君を度々訪ねて、魚釣を楽しんだという」
さて、本題である福沢諭吉「痩我慢の説」による勝海舟と榎本武揚への批判に入りたい。
福沢諭吉は天保5年(1835)生まれ、明治34年(1901)六十六歳で逝去。中津藩士、幕臣を経て新聞時事新報の創刊・発行者、東京学士会院(現在の日本学士院)初代会長、慶應義塾創設者であり「学問のすすめ」「文明論の概略」「西洋事情」その他多く名著を残し、明治日本社会に大きな影響を及ぼした啓蒙思想家である。
また、興味深いことに明治維新の年(1868)には三十三歳であって、福沢の前半は江戸時代、後半が明治時代と維新を境にして半分ずつの人生を送っている。
「痩我慢の説」は二十世紀を迎えた1900年(明治三十三年)の、翌年の1901年(明治34年)一月一日から時事新報に掲載が開始された。しかし、実際に書かれたのは、これより十年前の明治二十四年(1891)であった。
福沢ほどの人物が、新聞紙上で特定の人物を名指しで、それも明治政府の重鎮として存在感を示していた二人を批判するということ、それにはそれなりの背景と理由があるわけで、これについては後述するとして、まずは明治24年に書き終え、二人に送った際の手紙と、二人からの返書を見てみよう。(「日本の名著33福沢諭吉」中央公論社)
「福沢諭吉の手簡」
拝啓つかまつり候。のぶれば過日痩我慢の説と題したる草稿一冊を呈し候。あるいは御一読もなし下され候や。その節申し上げ候とおり、いずれこれは時節を見計らい、世に公にするつもりに候えども、なお熟孝つかまつり候に、書中あるいは事実の間違いはこれあるまじきや、または立論の旨につき御意見はこれあるまじきや、小生の本心はみだりに他を攻撃して楽しむものにあらず、ただ多年来、心に釈然たらざるものを記して世論に質し、天下後世のためにせんとするまでの事なれば、当局の御本人において云々のお説もあらば拝承いたしたく、何とぞお漏らし願いたてまつり候。要用のみ重ねて申し上げ候。
匆々(そうそう)頓首。
二月五日 諭吉
・・・・様
なおもってかの草稿は極秘にいたしおき、今日に至るまで二、三親友のほかへは誰にも見せ申さず候。これまたついでながら申し上げ候。以上。
「勝安芳の答書」
古より当路者、古今一世の人物にあらざれば、衆賢の批評に当たる者あらず。計らずも拙老先年の行為において御議論数百言、御指摘、実に慙愧に堪えず、御深志かたじけなく存じ候。
行蔵は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与(あずか)らず我に関せずと存じ候。各人へお示しござ候とも毛頭異存これなく候。おん差し越しの御草稿は拝受いたしたく、御許容下さるべく候なり。
二月六日 安芳
福沢先生
拙、このほどより所労平臥中、筆を採るに懶(ものう)く、乱筆御海容を蒙りたく候。
「榎本武揚の答書」
拝復。過日お示し下され候貴著痩我慢中、事実相違の廉(かど)ならびに小生の所見もあらば云々との御意、拝承いたし候。昨今別して多忙につきいずれそのうち愚見申し述ぶべく候。まずは取り敢えず回音かくのごとくに候なり。
二月五日 武揚
福沢諭吉様
では、福沢はどのような批判を「痩我慢の説」で展開したのであろうか。その要点と思われるところを拾ってみる。(「日本の名著33福沢諭吉」中央公論社)
まずは勝海舟に対する批判から紹介したい。
「自国の衰頽(すいたい)に際し、敵に対してもとより勝算なき場合にても、千辛万苦、力のあらん限りを尽くし、いよいよ勝敗の極に至りて、はじめて和を講ずるか、もしくは死を決するは、立国の公道にして、国民が国に報ずるの義務と称すべきものなり。すなわち俗に言う痩我慢なれども、強弱相対していやしくも弱者の地位を保つものは、単にこの痩我慢によらざるはなし」
「しかるにここに遺憾なるは、わが日本国において今を去ること二十余年、王政維新の事起こりて、その際不幸にもこの大切なる痩我慢の一大義を害したることあり。すなわち徳川家の末路に、家臣の一部分が早く大事の去るを悟り、敵に向かいてかつて抵抗を試みず、ひたすら和を講じてみずから家を解きたるは、日本の経済において一時の利益を成したりといえども、数百千年養い得たるわが日本武士の気風を傷(そこの)うたるの不利はけっして少々ならず。得をもって損を償うに足らざるものと言うべし」
「国家存亡の危急に迫りて勝算の有無は言うべき限りにあらず。いわんや必勝を算して敗し、必敗を期して勝つの事例も少なからざるにおいてをや。しかるを勝氏はあらかじめ必敗を期し、そのいまだ実際に敗れざるに先んじて、みずから自家の大権を投棄し、ひたすら平和を買わんとて勉めたるは者なれば、兵乱のために人を殺し、財を散ずるの禍をば軽くしたりといえども、立国の要素たる痩我慢の士風を傷うたるの責めは免るべからず。殺人、散財は一時の禍にして、士風の維持は万世の要なり。此を典して彼を買う、その功罪相償うや否や、容易に断定すべき問題にあらざるなり」
「然りといえども勝氏もまた人傑なり。当時、幕府内部の物論を耕して旗本の士の激昂を鎮め、一身を犠牲にして政府を解き、もって王政維新の成功を易くして、これがために人の生命を救い、財産を安全ならしめたるその功徳は少なからずと言うべし。
この点につきてはわが輩も氏の事業を軽々看過するものにあらざれども、ひとり怪しむべきは、氏が維新の朝にさきの敵国の士人と並び立って得々名利の地位に居るの一事なり」
「氏の尽力をもって穏やかに旧政府を解き、よってもって殺人・散財の禍を免れたるその功は、奇にして大なりといえども、一方より観察を下すときは、敵味方相対していまだ兵を交えず、早くみずから勝算なきを悟りて謹慎するがごとき、表面には官軍に向かいて云々の口実ありといえども、その内実は徳川政府がその幕下たる二、三の強藩に敵する勇気なく、勝敗をも試みずして降参したるものなれば、三河武士の精神に背くのみならず、わが日本国民に固有する痩我慢の大主義を破り、もって立国の根本たる士気を弛めたるの罪は遁(のが)るべからず」
この福沢諭吉の論旨になるほどと思う。立国の精神に立てば、あくまでも戦うことが必要で、一旦退く癖を国家政治が身につければ、外交問題で敵国から圧し込まれるばかりになってしまうという懸念を強調していることに同感する。
今の日本政府要人には、福沢が述べている痩我慢がなく、外交問題を目先にとらわれた安直な解決手段を弄しているような気がしてならない。政府要人は福沢の「痩我慢の説」を熟読玩味すべきであろう。
だかしかし、鉄舟の行動をつぶさに検討し、この連載を続けている者としては、福沢の言い分は筋が通ってはいるが、何か現実味が薄いという感を持たざるを得ない。
海舟という人物への好き嫌いは別として、海舟の成し遂げた業績は、鉄舟という際立った実践行動力をもった人物から命を賭する武士道精神を引き出し、共に能力の全てを傾注し、江戸無血開城をまとめ上げ、幕末から明治維新への混乱期を最小限の紛争にとどめ、日本国を近代化へと道筋をつけた最大の功労者であろう。また、この間、海舟も鉄舟も何度も刃の下をくぐる危機を経験してきている。
これに対し、福沢は同時代を学者・教育者としての道を歩んできた。福沢の教育観は、数と理をもととして、自然の法則に重きをおく科学的・合理的精神と、他方、独立自尊をモットーとし、いやしくも卑劣なことは絶対しないという精神、この二つの原則に立つものであった。
福沢は大坂に生まれ、父の死で大分県中津に移り住んで19歳まで育った。中津での幼少期の出来事としては、神罰を恐れず、稲荷神社の神体のお札を捨ててしまうという行動をとったこと、これは集団と伝統からの拘束を嫌い、自由でありたいという思考をもっていたことを表している。
その後、長崎でオランダ語を学び、大坂に出て緒方洪庵の適塾で三年間の修業で、後年の思想の礎と教育者としての性格形成を成したといわれている。
23歳で江戸に出て、25歳には海舟が艦長の咸臨丸でアメリカへ、その際に海舟と福沢はあまり仲が良くなかったといわれ、次に26歳で幕府の遣欧使節団翻訳方としてヨーロッパへ、32歳の慶応三年幕末動乱期には日本を留守にし、幕府の軍艦受取委員の随行として再度アメリカへ渡航している。
翌慶応四年四月32歳のときに蘭学塾を慶応義塾と改称、芝新銭座(有馬家中屋敷の一部、現在の東京都港区浜松町1丁目、神明小学校あたり)に開設し、彰義隊壊滅の日も「いかなる変動があろうとも、慶応義塾が存する限り、わが国に学問の命脈の絶えることはない」と通常の授業を続けたことは有名である。
このように福沢は、政治的なものへは傍観者的であり、政治とは独立した学問的な合理性を重んじたのであって、幕末政治に深く関わっていた海舟や鉄舟とは大きく立場が異なる。当然ながら後年、海舟は福沢の批判について反論したが、これは次号にお伝えしたい。
